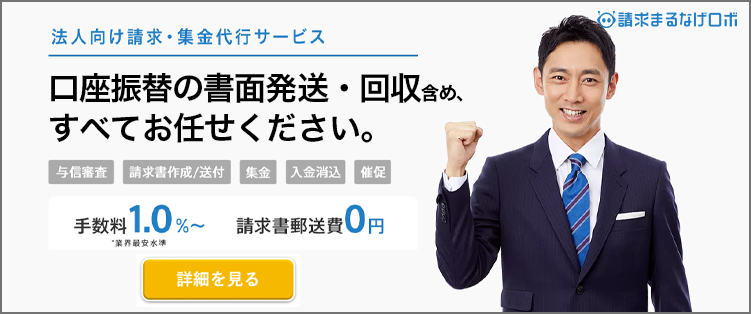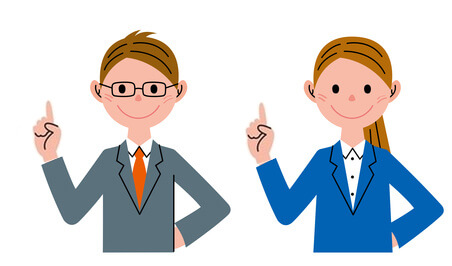口座振替(口座引き落とし) の仕組みとは?メリット・デメリットや残高不足の影響も解説!

通販の定期コースや頒布会、サービスの会員料金など、定期的な支払いが生じるケースは多いものです。
こうした支払いを毎月自動で完了する仕組みがあれば、事業者にもお客様にもメリットが大きくなります。その手段の1つが口座振替(口座引き落とし)です。
日本では昔から水道料金、ガス料金、電気料金などの公共料金を銀行口座から引き落とす決済手段として広く用いられています。
これは海外ではあまり見られない決済手段で、海外の国々ではサービス利用者が毎月送られて来る請求書に小切手を同封して事業者に送り返すという支払い方法が一般的です。
このように手間のない口座振替は、日本独自の優れたシステムとして発展してきました。
今回は口座振替の仕組み、口座振替のメリット・デメリットのほか、口座振替における残高不足の影響などにも触れて解説します。
口座振替(口座引き落とし)とは

口座振替(口座引き落とし)とは、金融機関の口座から請求金額を自動的に引き落とし、指定の口座に振り替えるサービスです。「自動引き落とし」「自動振替」「口座自動振替」と同じ意味で使われています。
口座振替は一度登録すれば口座から請求金額を自動で引き落としてくれるため、公共料金や通信料、月謝や会費、定期購入や授業料など、継続的な代金回収を行うビジネスの集金に優れています。
はじめにWebや対面で口座振替依頼書を提出すれば、あとは自動で銀行口座から引き落としがされるので、 お客様は入金に出向く必要がなくなり、支払いの手間を省くことができます。
従来の口座振替の手続き方法では、書類を書いたり、郵送したり、と登録完了まで時間と手間がかかる問題がありました。また、記入ミスなどがあった場合は最初からやり直すケースもあるため、利用開始までにタイムラグが発生するのも口座振替のデメリットでした。
しかし、現在取り入れられているWeb(ネット)口座振替であれば、これらの作業をオンライン上で進められるため、スムーズに利用が開始できるようになっています。
口座振替(口座引き落とし)の仕組み
口座振替(口座引き落とし)の仕組みは、主に以下の5つから成り立っています。
1.データ交換:銀行と収納企業(消費者にサービスを提供した事業者)の間には、全銀協(全国銀行協会)が管理する「全銀システム」というネットワークインフラが存在します。このシステムを通じて口座振替データがやりとりされます。
2.口座振替データの作成:収納企業は引き落としを行う口座振替対象者の情報(口座番号、金額、口座振替日など)をデータ化し、取引銀行に送信します。
3.データ処理プロセス:収納企業からのデータは各銀行のシステムに取り込まれ、以下の3つの処理が行われます。
・銀行は口座振替日に一括処理を実行
・各口座振替対象者の口座から指定額を引き落とし
・合計金額を収納企業の口座に入金処理
4.照合システム:銀行は口座振替結果(引き落としの成否)のデータを作成し、収納企業に返送します。
5.入金消込処理:収納企業は受け取った結果データを自社の顧客管理システムと照合し、入金処理(消込処理)を行います。
勤め先や自身のビジネスの決済手段に口座振替を行う場合、以上のようなステップを踏んで処理が行われます。
口座振替を導入するには、金融機関ごとに直接契約を結ぶ方法と、当社の「サブスクペイ」のような決済代行会社のサービスと契約を結ぶ方法があります。
なお、法人・個人を問わず、事業者が口座振替(口座引き落とし)を導入する方法については、以下で詳しく解説しています。
口座振替(口座引き落とし) と振替の違い
ここで注意が必要な「口座振替」の違いにも触れておきましょう。
前述の通り、口座振替(口座引き落とし)とは、金融機関の口座から請求金額を自動的に引き落とし、指定の口座に振り替えるサービスです。一方、振替とは、「同一銀行同一支店内の本人の口座間で資金を移動させること」を指します。
口座振替のサービスに「振替」という言葉を用いるのは、口座振替の依頼を受けた銀行・金融機関が、「行内にある消費者の預金口座」の資金を「行内にある各収納企業への送金用口座など」へ移動をするためです。
収納企業への振込を行う主体が、口座の持ち主である消費者本人ではなく、銀行・金融機関であるため、消費者側からすると第三者宛ての資金移動であっても、銀行・金融機関としては「振替」という言葉を使うのです。
口座振替(口座引き落とし) と請求書の違い
もう一つ、勘違いされやすい口座振替(口座引き落とし) と請求書の違いについても、触れておきましょう。
口座振替と請求書はどちらも後払いをする点が似ています。
一方、口座振替と請求書払いは、口座振替が「金融機関の口座から請求金額を自動的に引き落とす」のに対し、請求書払いは「届いた請求書の支払い期限までに自分で支払う必要がある」という点で明確に違いがあります。
どちらの支払い方法にも長所と短所があるので、支払う金額の性質やビジネス・生活のスタイルに応じて、適切な方法を選択することが重要です。
請求書払いについては、以下で詳しく解説しています。
事業者が口座振替(口座引き落とし)を導入するメリット

では、次に事業者が口座振替(口座引き落とし)を導入するメリットをご説明しましょう。
事業者が口座振替サービスを導入する主なメリットが、以下の5点です。
代金未払いリスクを抑えられる
サービスを利用した消費者から代金の払い込みがなければ、企業の資金面は悪化し、ひいては倒産に至る可能性さえあります。
しかし、口座振替(口座引き落とし)を導入していれば、こうした代金未払いのリスクを最小限に抑えられます。口座振替による代金回収率は90%以上とされているため、安定した資金繰りを実現できるでしょう。
口座振替が設定された口座から自動で請求金額が引き落とされるため、消費者側が忘れていたことによる振込漏れや延滞といったミスを低減できます。
継続利用率の向上が見込める
サービスを利用する消費者にとって、月々の支払いを意識するタイミングは解約のきっかけになりやすいものです。口座振替(口座引き落とし)で代金回収を自動化することで、サービス利用継続率の向上にもつながります。
集金業務の効率化を図れる
口座振替(口座引き落とし)によって消費者からの支払いがスムーズになると、事業者側の集金業務の効率化にもつながります。
基本的に、集金業務は「事業者が消費者に請求して終わり」ではありません。過剰入金の払い戻し作業や入金不足による追加入金の依頼など、さまざまな請求業務が発生します。一つの未払いを解決するのに、たくさんの時間や工数が必要となることも珍しくありません。
これに対して、口座振替は毎月決まった金額を自動で引き落とすため、導入することで未払いの処理にかかっていた工数を大幅に削減することができます。
顧客層の拡大につながる
クレジットカードを持つ方が増えていますが、その一方でクレジットカードを持たない方も一定数います。
そういった方が、使用できる決済手段がないために皆様の商品やサービスの購入を断念されることになれば、新規顧客の獲得は難しくなってしまいます。
口座振替(口座引き落とし)は半世紀以上前から導入され、多くの人にとって馴染みのある決済方法であるため、クレジットカード決済が弊害となって獲得できなかった新たな顧客層の獲得も望めるでしょう。
代金回収コストを削減できる
期日までに代金が回収できない場合、確認の連絡として請求書を再送したり、それでも動きがない場合は催促状を送ったりするのが一般的です。
しかし、この業務には、請求書や催促状の印刷・封入・郵送など、さまざまなコストが発生します。
しかし、口座振替(口座引き落とし)は毎月決まった金額を自動で引き落とすため、導入することでこれらのコストが発生する率を最低限に抑えることができます。
未回収0件とまではいかないかもしれませんが、催促に至る案件が減ることは必要以上の出費をしなくて済むことになるため、企業にとっては立派なメリットといえるでしょう。
事業者が口座振替(口座引き落とし)を導入するデメリット
事業者側が口座振替(口座引き落とし)を導入する主なデメリットは、以下の3点です。
手続きや運用が煩雑
口座振替(口座引き落とし)は、指定口座からの自動引き落としを開始するまでの手続きに手間が掛かります。まず、利用者の指定口座を自動引き落とし先として登録するには、金融機関に口座振替依頼書を提出しなければなりません。
この書類には消費者側が引き落としを希望する口座の銀行名や口座番号などの口座情報を記入し、届け印を捺印する必要があります。口座情報の誤りや記入漏れ、印鑑相違などの不備があると金融機関は手続きを進めることができません。
この場合は、再度利用者から正しい口座情報が記入された口座振替依頼書を提出してもらうための事務手続きが発生します。
ECサイトのように利用者と直接対面しない事業形態の場合、消費者側と郵送で書面のやりとりを行うため、運用上の煩雑さを産む原因になります。
入金までタイムラグがある
上述した口座振替依頼書を金融機関に直接もしくは決済代行会社を介して提出するいずれの場合でも、提出から実際に口座振替(口座引き落とし)が開始できるようになるまで、1~2ヶ月かかります。
その間は事業者への入金がないため、口座振替開始可能日よりも前に消費者から代金を徴収する必要がある場合は、他の決済手段を用意せねばなりません。
また、口座振替開始後も、消費者の口座から引き落としを実施した日から実際に事業者の口座に入金されるまでには、数日間のタイムラグが発生します。
タイムラグの日数は金融機関や決済代行会社によって異なりますが、10日前後はかかるのが一般的です。商材の仕入れや関係会社への支払いなどの日程を鑑みて、キャッシュフローの観点において問題がないかを確認する必要があります。
残高不足による未回収リスクがある
口座振替(口座引き落とし)は、他の決済手段よりも高い代金回収率がありますが、残高不足による未回収リスクをゼロにはできません。残高不足で未回収になるのは、主に次の2つのケースです。
1つ目は、消費者側がサービスを利用中であることを忘れてしまったり、口座振替によって代金を支払っていることを忘れていたりするケースです。
このケースは、口座振替が消費者に利便性をもたらす半面、ともすると代金支払いに対する意識を遠ざけてしまいがちなことから引き起こされる未回収事例といえるでしょう。
2つ目は、給与口座が口座振替に指定されているケースです。引き落とし日が給料日よりも前に設定されている場合、残高不足になる確率はどうしても高まります。
こうしたケースに備えて、消費者側の口座に不足分が補填された時点で改めて自動で引き落とす旨の契約を結んでおくことは大切です。ただし、引き落としの回数が増えると、金融機関への手数料も増えるため、注意が必要です。
消費者が口座振替を利用できるメリット
ここまで、事業者側の視点を中心に解説してきましたが、口座振替(口座引き落とし)は顧客にとってもメリットの大きい支払い方法です。
顧客が口座振替を利用できる主なメリットとしては、以下の3点です。
支払いの手間がなくなる
口座振替(口座引き落とし)を利用することで、消費者側は毎月銀行やATMまで支払いに行く手間がかからなくなります。
毎月振込を利用していると、時に振込期日を間違えたり入金金額を間違えたりする可能性もあるでしょう。しかし、口座振替を導入していれば、そのような心配は不要になります。
決済がスムーズに行われるようになれば、消費者側も商品購入までのハードルが下がり、今まで以上に買い物が楽しめるようになるでしょう。
クレジットカードを使う必要がない
ECサイトなどを利用する場合には、クレジットカードによる決済は非常に便利です。しかし、クレジットカードの契約には年齢や年収といった条件もあります。こういった条件から契約ができなかったり、個人情報の流出などを恐れてクレジットカードを持たない判断をされる方もいます。
そのような消費者も、口座振替(口座引き落とし)を利用することで、個人情報の流出を心配せずにサービスや商品を購入することが可能となります。
手続きや運用が煩雑
口座振込で代金を支払う場合、どうしても手数料がかかるという難点があります。その点、口座振替(口座引き落とし)なら消費者側には手数料がかかりません。
振込手数料は、1回200~300円ほどの出費かもしれませんが、支払金額や取引頻度が多い場合は、消費者側の負担にもなり得ます。口座振替によって手数料がかからないとなれば、消費者側としても、サービス利用や商品購入のハードルが下げるでしょう。
消費者からみた口座振替を利用するデメリット
消費者からみた口座振替(口座引き落とし)を利用するデメリットは、以下の通りです。
振込手数料がかからない
事業者側のデメリットでも挙げましたが、消費者側からみても、事前に手続きが必要な点は、口座振替(口座引き落とし)を利用するうえでデメリットといえます。
銀行印と書類の印鑑が異なっていたり、口座名義が間違っていたりすると修正作業が発生するため、開始の際に手間がかかる面があります。
しかし、一度利用を開始できればこれ以降は自動で支払われるので、長く継続して支払う場合は口座振替を利用した方が便利といえます。
口座振替を導入する際の決済代行会社の選び方

では、口座振替の導入に決済代行会社を利用する場合に焦点を当て、決済代行会社の選び方についてお伝えしましょう。
自社にマッチした決済代行会社を選ないと、せっかく導入しても業務の効率化が図れない可能性があるので、以下の点に注意してみてください。
金融機関の対応範囲
決済代行会社を通して口座振替を行うメリットは、サービス提供事業者がたくさんの金融機関と個別で手続きをする必要がない点です。したがって、決済代行会社がどれだけ多くの金融機関と口座振替の契約を結んでいるかで利便性が変わります。
なお、当社の「サブスクペイ」をご利用いただくと、都市銀行・インターネット銀行・信託銀行・特殊銀行・外国銀行・ゆうちょ銀行・第一地方銀行・第ニ地方銀行・信用金庫・商工中金・信用組合・労働金庫・県信連・農協・漁連といった日本全国の1000以上の金融機関口座で、口座振替を導入いただくことができます。
費用・手数料
決済代行会社と口座振替の契約するにあたっては、初期費用・月額費用・決済手数料などをランニングコストとして勘案しておく必要があります。
料金の詳細についてはホームページ上で公開されていないことも多く、その他の利用料があるかも含めて事前に見積もりを取ることは欠かせません。
できれば数社から見積もりを取って、料金相場の適正値を探るようにしましょう。
なお、当社の「サブスクペイ」で口座振替を導入する場合、初期費用0円、決済手数料85円〜となっております。
対応する決済手段の豊富さ
決済代行会社と契約する際、口座振替だけでなくクレジットカード決済などの他の決済手段も導入したいことも多いでしょう。
決済代行会社によって、対応している決済手段は異なるため、自社のニーズに合った決済手段に対応しているか、あらかじめ確認しておくことが大切です。
なお、当社の「サブスクペイ」では、口座振替以外にも、クレジットカード決済、銀行振込・バーチャル口座、コンビニ決済、掛け払い決済(債権保証付き)、BtoB向けSalesforce決済など多様な決済手段に対応しております。
セキュリティ対策と信頼性の確保
決済代行会社と口座振替の契約するにあたっては、セキュリティ対策が万全かも重要なポイントです。
サブスクペイを導入すると、PCI DSS 4.0(クレジットカード業界におけるグローバルセキュリティ基準)への準拠・プライバシーマークとISMS(JIS Q 27001:2014)認証の取得により、強固なセキュリティ対策がされたサービスをご利用いただけます。
このような多層的なセキュリティ対策により、口座振替をはじめとする多様な決済手段の導入で最も重要な「信頼性」を確保できます。これにより、顧客は安心して決済情報を入力し、継続的な取引を行うことができます。
▼サブスクペイのセキュリティ基準

実績と信用
決済代行会社と口座振替の契約するということは、自店舗の売上管理の一部を任せるということです。そのため、安心して任せられるサービス・会社かどうかを確認しなければなりません。
利用開始後にシステムトラブルが発生したり、売上金が正しく振り込まれなかったりすることがないようにしましょう。
まずは決済代行会社のホームページなどを調べて、導入実績があるかを調べることをおすすめします。
単なる導入社数や取引件数などの数字だけではなく、具体的な社名を公開している方がより信頼できます。
特に、大手企業や有名企業、自社と同じ業種の企業などに導入実績があれば、導入後のトラブル発生リスクは避けられるでしょう。
なお、当社の「サブスクペイ」は、大手から中小、個人事業主まで 14,000社以上の導入実績があり、年間500億円以上の取引に活用いただいております。
用途としても、Webサービス/システム利用料、コンテンツ配信費、物品レンタル費、寄付/募金、メディア掲載費/広告費、オンラインサロン会費、団体/協会会費、メルマガ配信費、塾/スクール/ジム月謝、コンサルティングなど幅広くご活用いただいております。
具体的な導入事例については、以下で紹介しています。
サブスクペイ導入事例
口座自動振替の導入は「サブスクペイ」にお任せ!

自社のビジネスに口座自動振替を導入されたい場合は、ぜひ「サブスクペイ」をご検討ください。
導入企業様からは「決済手数料が90%削減され、数百万円規模のコスト削減が実現した」といった好評価をいただいております。
また、決済連動の顧客管理データベースにより、ファンクラブ会員、メール会員、有料コンテンツ会員など、あらゆる会員管理業務に最適な機能を備えたソリューションを提供。利用状況の見える化で単価アップや解約防止に寄与するとともに、顧客属性・行動情報・売上予測の見える化によってネクストアクションの策定・投資判断などにお役立ていただけます。
さらには、業界最安水準の手数料2.65%~、顧客管理と決済処理をひとつのクラウドに集約したことによる間接費の削減により、導入するだけでコストダウンを実現できます。
なお、気になる対応決済手段についても、クレジットカード決済・口座振替・銀行振込・バーチャル口座・コンビニ決済など幅広く搭載。顧客に合わせた柔軟な課金モデルの設計が可能です。決済代行会社の安全なサーバー内に顧客情報を預けて管理するため、導入事業者様の情報管理負担、セキュリティ負担も解消します。
これまで株式会社ROBOT PAYMENTは、決済代行業として20年以上にわたり、決済代行事業を行ってまいりました。サブスクペイは大手から中小、個人事業主まで累計14,000社以上の導入実績があり、年間500億円以上の取引に活用いただいております。決済導入フローについても、審査提出から最短5営業日で稼働が可能です。
オンライン決済の導入やサブスクリプションビジネスにおける顧客管理・課金設計などにお悩みのご担当者様は、株式会社ROBOT PAYMENTの「サブスクペイ」までお気軽にご相談ください。
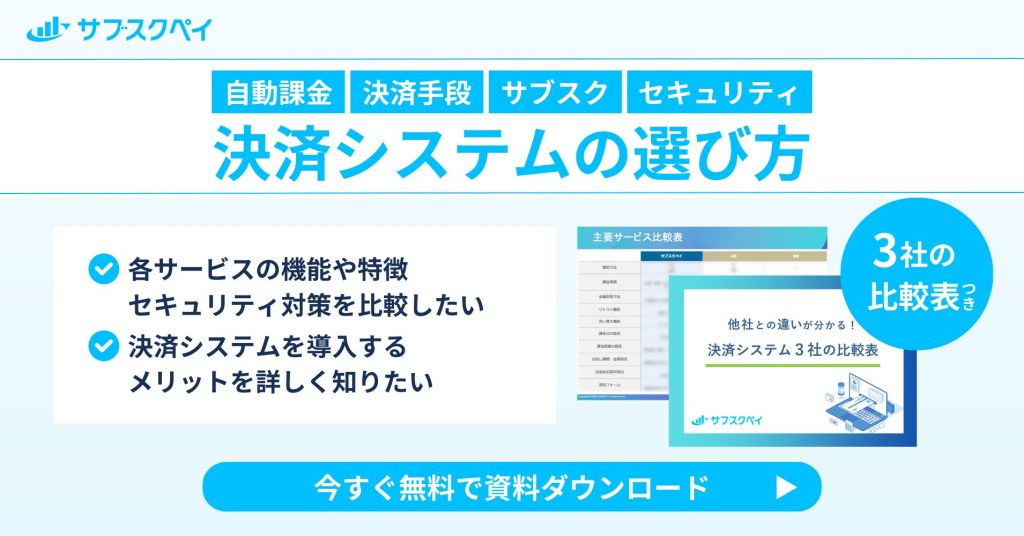
※一部サービス提供元の運営記事です/PR