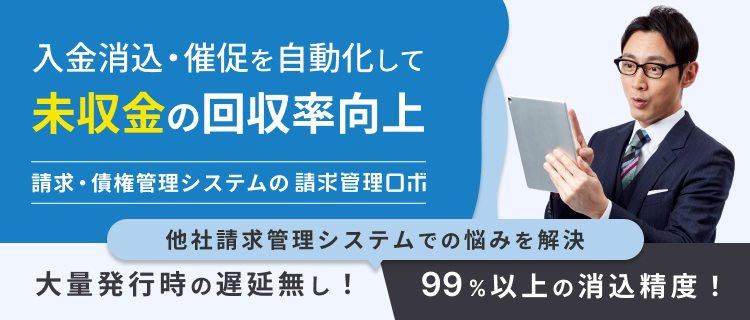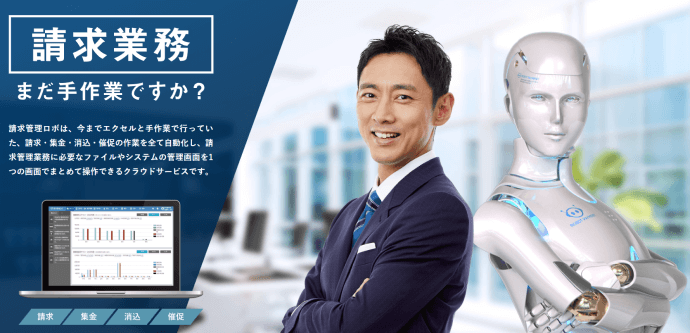請求書の保存期間とは?経理書類の保存年数や請求書の保管方法も解説

企業経営をするうえで、書類は日々増えていくものです。請求書をはじめとする経理関係書類の保管に頭を悩ませている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで本記事では、そもそも請求書はなぜ保存義務があるのか、請求書は何年間保存する必要があるのか、請求書を保管する際の方法などについて解説し、加えて請求書以外の経理関係書類はどの程度の保存する必要があるのかについてもご説明します。
請求書には保存義務がある

請求書は、企業間で実際に取引が行われたことを証明する「証憑書類」と呼ばれる書類です。証憑書類は所得税法や消費税法、法人税法などで一定期間保存することが定められており、会社の判断で勝手に破棄することは認められていません。
また、請求書については、税制上の規定により原本を保存しておくことが定められています。コピーや写しだと、請求書の偽造や不正会計が起きてしまうリスクがあるため、必ず受け取った請求書の原本を保存するようにしてください。
ただし、請求書の保存義務が課されるのは「受け取った請求書」で、実は請求書を発行した側には保存義務が課されません。例外として、入金の確認のためなどに請求書の控えを発行している場合は、控えを保存する必要があります。つまり、控えを発行している企業は「受け取った請求書」と「発行した請求書の控え」をしっかりと保存しておき、控えを発行していない企業は「受け取った請求書」のみ保存しておけば問題ないということです。
請求書のほかにも、領収書や納品書といったさまざまな書類が証憑書類に含まれ、税務調査の対象となります。保存期間は書類によって異なるため、担当者はあらかじめ各文書の保存期間をチェックしておきましょう。
請求書の保存期間

請求書の保存期間は、個人事業主は最低5年間、法人は最低7年間と定められています。これは電子請求書の場合も同様です。
ただし、企業の形態や状況によって保存期間が異なってくるケースがあります。以下で詳しくみていきましょう。
法人の請求書の保存期間は、原則7年間
先述の通り、法人の請求書の保存期間は、原則として7年間です。税務署は、原則として過去7年間の会社の経理状況を調べることができます。そのため、7年分の請求書を保存しておくことで、もし税務調査が入っても、きちんと対応することができます。
保存期間の「7年間」の起算は、請求書が発行された日からではなく、その請求書が含まれる会計年度の確定申告書の提出期限の翌日から始まります。例えば、3月で会計年度が終わる会社の場合、確定申告書を5月末までに提出します。そのため、その会計年度の請求書は、5月末から7年間保存する必要があります。
ただし、法人が赤字となった年度の請求書については、欠損金の繰越期間に合わせた期間保存する必要があります。 赤字が生じると将来の黒字と相殺できる欠損金ですが、その繰越期間は、一般的に10年であるため、実務上は赤字となった年度の請求書も10年間保存することが多いです。
個人事業主の請求書の保存期間は、原則5年間
個人事業主の請求書の保存期間は、青色申告・白色申告のどちらの場合も原則として5年間です。ただし、この5年間の数え方は、請求書を受け取った日や発行された日からではありません。その請求書が使われた年の確定申告の締切日から、5年間保存する必要があります。
また、売上の規模によって、消費税の扱いが変わってきます。2年前の売上が1,000万円以下の場合は、消費税の支払いが免除される「消費税免税事業者」になれます。一方、1,000万円を超えると「消費税課税事業者」となり、この場合は請求書を7年間保管しなければなりません。
青色申告を選んでいる個人事業主の方は、帳簿や書類をきちんと保管することが特に大切です。もし必要な書類を捨ててしまうと、青色申告の許可が取り消されてしまう可能性もあります。そのため、安全のために個人事業主であったも請求書は7年間保存しておくことをお勧めします。
保存義務のある経理書類と保存年数

保存義務がある経理書類は、決して請求書だけではありません。ここからは、保存義務がある書類の種類を保存年数別に紹介します。
5年以下の保存が必要な書類
5年以下の保存が必要な書類としては、労働安全衛生法や雇用保険法、労働基準法などに該当する、従業員に関わる書類が多い傾向にあります。
それぞれの保存年数と書類の種類は、以下のとおりです。
| 2年間 | 健康保険に関する書類、雇用保険に関する書類、厚生年金保険に関する書類 | |||
| 3年間 | 労働者名簿、賃金台帳、労災に関する書類、雇入・解雇・災害補償・賃金その他労働関係に関する重要な書類、労働保険料の徴収に関する書類、衛生委員会議事録、安全委員会議事録、安全衛生員会議事録 | |||
| 4年間 | 雇用保険の被保険者に関する書類 | |||
| 5年間 | 一般健康診断個人票 | |||
7年間の保存が必要な書類
7年間の保存が必要な書類としては、決済・決算の際に作成された経理関係の書類や給与所得者の扶養控除等申告書など、お金に関わるものが多く挙げられます。これらの書類は所得税法や法人税法などによって保存が義務付けられており、税務調査で不備が発覚すると企業会計の信用性が下がってしまうため、十分に注意しましょう。
7年間の保存が必要となるおもな書類は、以下のとおりです。
| 経理・税務書類 | 領収書、見積書、請求書、総勘定元帳、貸借対照表、損益計算書、決算に関して作成された書類、仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、注文書、契約書 | |||
| 人事・労務書類 | 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書、源泉徴収簿、従業員の身元保証書、誓約書 | |||
10年間の保存が必要な書類
商法によって定められている商業帳簿や営業活動に関する重要書類などは、10年間の保存が義務付けられています。
10年間の保存が必要となるおもな書類は、以下のとおりです。
| 経理・税務書類 | 計算書類および附属明細書、会計帳簿および事業に関する重要書類、財務関係書類、月次・年次決算書類 | |||
| 重要書類 | 株主総会議事録、取締役会議事録、監査役会議事録、委員会議事録、重要会議の議事録、製品の取引に関する記録、損害保険に関する重要な文書、社内全般の通達に関わる文書、福利厚生に関する重要な文書、経営管理のために重要で後列となる文書 | |||
永久保存の書類
登記関係書類や知的所有権、特許や訴訟関連の書類、会社の定款などは、永久保存が必要な書類です。法令では定められていませんが、保存しておかないと後々不都合が生じてしまう可能性が非常に高いため、忘れずに保存しておきましょう。
10年間の保存が必要となるおもな書類は、以下のとおりです。
| 企業経営に関わる書類 | 定款、株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿、端株原簿、株券喪失登録簿、登記・訴訟関係書類、官公庁への提出文書、官公署からの許可書・認可書、通達などに関する重要な書類、知的所有権の関係書類、社規・社則およびこれに類する通達文書、効力の永続する契約に関する文書、重要な権利や財産の得喪等に関する文書、社報・社内報、重要刊行物、製品の開発・設計に関する重要な文書 | |||
| 人事・労務書類 | 重要な人事に関する文書、労働組合との協定書、表彰や懲戒に関する文書、従業員の労務・人事・給与・社会保険関係の書類 | |||
請求書を保管しておく方法
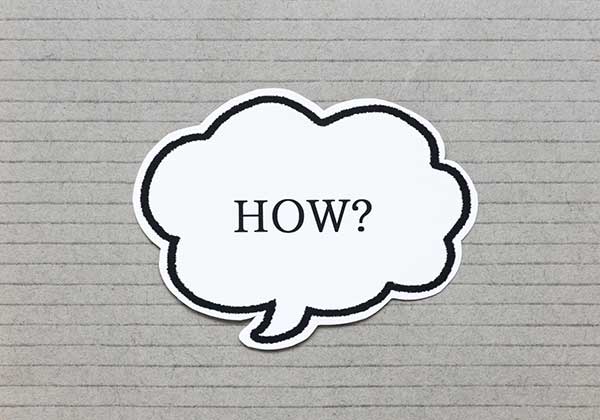
請求書の保管方法は、従来の紙媒体での保管のほか、電子データやマイクロフィルムで保存する方法があります。とくに近年は「管理しやすい」「スペースを取らない」と、紙媒体の保管から電子データによる保管に切り替える企業や個人事業主が増えてきています。それぞれの保管方法について詳しく解説します。
紙媒体での保管
ペーパーレス化やIT化が進んだ近年でも、印刷した請求書を郵送してやり取りをしている企業は多いものです。請求書が送られてくる場合は、取引先や月別でまとめてファイリングして保管している企業がほとんどでしょう。
紙媒体で請求書を保管するのはもっとも一般的な方法ですが、以下のようなデメリットがあるため注意が必要です。
・手動振り分けによるミスのリスク
・経年劣化による破損や紛失の可能性
・保管スペースの占有
・検索性が悪く、探しにくい
とくに課題なのが、保管スペースの問題でしょう。7年分の請求書や契約書などの書類は、非常に多くのスペースを必要とします。企業によっては専用の倉庫などを借りなくてはいけなくなることもあるため、管理の手間やコストがかかってしまいます。
また、2022年の電子帳簿保存法改正に伴い、2024年1月以降、電子取引した請求書を紙で保存することは完全にできなくなりました。紙でやり取りした請求書のみが、紙媒体のまま保管可能です。
電子データでの保管
また、紙でやり取りした請求書の保管は、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」における重要書類要件を満たした上で、電子データで行うことも可能です。紙の請求書をスキャナーなどで読み取るほか、デジカメやスマホで撮影したデータを保管することも認められています。とくに近年は「管理しやすい」「スペースを取らない」と、紙媒体の保管から電子データによる保管に切り替える企業や個人事業主が増えてきています。ハードディスクやCD、DVD、クラウドサーバなどで管理できるため、とにかく省スペースで検索性が高い点が大きなメリットです。
また先述したとおり、電子取引した請求書は、法改正に伴い紙保存が認められなくなり、電子データでのみ保存が認められています。その際は、電子帳簿保存法の「電子取引」要件を満たす必要があります。
請求書を電子データで保存する方法や要件について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
なお、当社の「請求管理ロボ」では、発行した請求書について、請求管理ロボ上で電帳法の保存要件を満たした形式で請求書の電子データの保管が可能です。
マイクロフィルムでの保管
マイクロフィルムとは、文書などをカメラで撮影し、10分の1から30分の1程度に縮小撮影する写真技法のことを指します。写真フィルムよりも細かい粒子で構成されるため、請求書だけではなく契約書や図面などの細かい文字や線まで記録できます。
請求書を縮小してフィルムに収めるため、紙媒体で保存するよりも大幅に省スペース化が可能です。長期保存に適していて法的証拠能力もあります。
ただし、マイクロフィルムを用いた保存が可能なのは最後の2年に限られてしまうため、法人の場合は6年目と7年目の請求書しかマイクロフィルム化できません。さらに専用の機材が必要になるため、請求書の保管方法として導入している企業はそう多くありません。
請求書の保存期間の心配も「請求管理ロボ」にお任せ!

「請求書の保存スペースが足りない」「電子請求書のデータ保管に心配がある」という経理ご担当者様も少なくないことと思います。そんなお悩みをお持ちでしたら、請求書の電子データを税法上の法定期間(7年間、または7年を越えて繰越欠損金の控除を行う場合はその控除期間中最長10年間)にわたって保存可能な、株式会社ROBOT PAYMENTが提供する「請求管理ロボ」の導入をぜひご検討ください。
「請求管理ロボ」は、毎月の請求業務を最大80%削減する請求管理システム(債権管理にも対応)です。請求書の発行や送付、集金、消込、催促などの売掛金管理を全て自動化し、人的作業を減らしてミスを防ぐとともに、経理業務の効率化を実現します。
加えて、SFA(販売管理システム)との連携により、自動で行われた請求業務の内容を会計システムに反映させることも可能です。これにより、煩雑なやり取りの削減と企業会計の透明化をサポートし、従業員がコア業務に専念できるようになります。
なお、コンビニ決済、クレジットカード決済、口座振替、銀行振込など、複数の決済手段に対応しているため、企業間取引のみならず、BtoC取引にも活用いただけます。
インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しており、これまでに700社以上の企業に導入され、年間取引請求金額は約2,770億円に上ります。経費の管理や帳簿付け、請求業務にお悩みの企業のご担当者様は、お気軽に「請求管理ロボ」にご相談ください。

※一部サービス提供元の運営記事です/PR