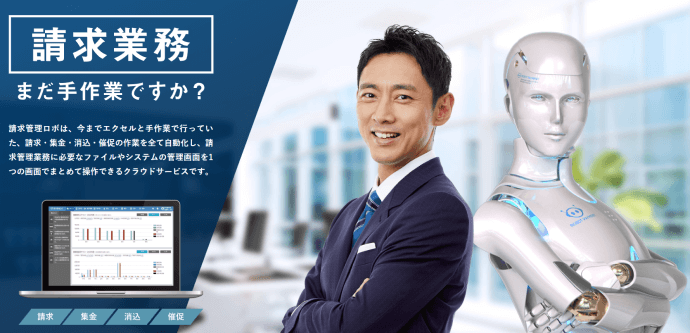電子帳簿保存法ではクラウド活用が鍵!対応できるクラウドサービスも紹介

経理の電子化による生産性向上を目的として、2022年には電子帳簿保存法の大幅な改正が行われました。電子帳簿保存法に対応するためには経理業務のクラウド化が急務といえるでしょう。しかし、クラウドサービスがなぜ必要なのか、どのようなクラウドサービスを選べば良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、クラウドサービスを導入するメリットや導入時の注意点、電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスなどについてご紹介します。
【無料EBOOK】 請求管理サービス7社を徹底比較!導入する際のポイントなども解説
電子帳簿保存法によるクラウドストレージの活用の促進について

電子帳簿保存法施行当初は、インターネットを介して利用する「クラウドストレージ」でのデータの保管・共有は認められていませんでした。しかし、2005年の法改正でスキャナ保存が認められてからは、クラウドストレージをはじめとする各種ツールの活用が推奨されています。ここでは、クラウドストレージの概要、基本機能、活用シーンをご紹介します。
クラウドストレージとは
インターネット上にデータを保管するサービスのことです。インターネット上でデータを保管するという点では、OSのファイル共有機能を利用した「ファイルサーバー」と似ていますが、アクセスできる範囲が異なります。具体的には、ファイルサーバーでは社内に閉じた範囲でのアクセスが基本なのに対し、クラウドストレージの場合、ストレージに対するアクセス権限を持っていれば、場所やデバイスに関係なくどこからでもアクセスが可能です。
基本機能
先述したように、クラウドストレージにファイルを保存しておけば、インターネット上に設置してあるストレージにログインするだけでどこからでもデータを閲覧できます。例えばオフィスではPCから、外出先ではモバイル端末からアクセスすることも可能です。
また、ストレージ上で直接編集も行えるため、逐一データをダウンロードする必要がありません。編集する際に便利なのが、更新した内容を自動保存する機能と複数の端末で編集したデータを同じ状態に保つ自動同期機能です。上記の2つの機能によって、ひとつのファイルを複数人で共有し、それぞれが常に最新データを確認することが可能になります。
活用する場面
クラウドストレージは、社内だけでなく、取引先などとデータを共有したい場合にも有効です。
企業では、日々書類や動画などでやり取りをする業務が発生します。特に、動画はアップロードやダウンロードなどに時間を要するため、メール添付で共有すると作業効率が低下する原因になるでしょう。クラウドストレージでは、これまでメール添付で送信していたデータも、URLを教えるだけで簡単に共有できるようになり、大幅な作業時間の短縮が実現します。ファイル・フォルダごとにアクセス制限をかけられるので、セキュリティ面においても安心です。
クラウドストレージ導入のメリット・デメリット

様々なシーンで活用できるクラウドストレージは、インターネット上のサービスの特徴である利便性・柔軟性を兼ね備えているほか、コストも安価なことから企業規模問わず導入しやすいでしょう。しかし、クラウドストレージの導入には、最低限のリスクがあることも理解しておかなければなりません。ここからは、クラウドストレージ導入のメリット・デメリットをご紹介します。
メリット
まずは、クラウドストレージを導入する主なメリットを3つご紹介します。
1つ目が、データ保存が容易になる点です。業務のデジタル化や書類の電子化を推進するには、データの保存場所が必要です。クラウドストレージでは、必要な容量の保管場所を安価で確保できるほか、拡張したい際にも簡単に対応できます。
2つ目が、多様な働き方に対応できる点です。コロナウイルスの感染拡大や働き方改革の影響もあり、近年はテレワークやリモートワークを導入する企業が増えています。電子化した書類の保存場所をクラウドストレージにすれば、どこからでもデータの閲覧・共有が可能なため、情報共有やコミュニケーションをスムーズに行えます。
3つ目が、災害時にも対応できる点です。災害が発生した際に、心配なのがパソコンやサーバーの破損です。クラウドストレージでは、インターネット上にデータが保管されているためログイン情報があればどの端末からでもログインできます。また、バックアップ機能にも優れており、オペレーションのミスなどで削除してしまったファイルも復元可能です。
デメリット
次に、デメリットとその対処方法を4つご紹介します。
まず1つ目が、オフライン下での使用ができない点です。クラウドサービスは、インターネット上にデータを保管するサービスなので、オンライン上での使用が前提となっています。そのため、アクセスするにはインターネット回線の整備が必要不可欠です。回線の強度によってパフォーマンスにも差が生まれるので注意しましょう。
2つ目が、カスタマイズが困難である点です。固定的なサービスであるため、自社に合わせたカスタマイズが難しいと傾向があります。ただし、豊富な機能を備えるサービスも多いため、自社の商品に適したサービスを選択できれば、オーダーメイドでシステムを構築するよりもコストや手間を抑えて電子化に対応できるでしょう。
3つ目が、トラブル時の対応がベンダー任せになる点です。インターネットを介したサービスなので、ネットワーク障害が発生することも少なくありません。しかし障害発生時に対応するのはベンダーとなるため、復旧までに時間がかかるケースもあります。障害時の対応体制が整っているかどうかも、導入前に確認しておきましょう。
4つ目が、情報漏洩リスクがある点です。クラウドストレージを利用するには、基本的はIDとパスワードが必要になります。そのため、ストレージ上のファイルの場所を示すURLが漏えいしたとしても、基本的にはアクセスできない仕組みです。しかし、ID・パスワードが流出した際には第三者にデータを閲覧・改ざんされるリスクがあります。対策としては、定期的なパスワードの更新や社内研修によるルールの徹底などが挙げられます。
電子帳簿保存法改正に向けた企業の準備

これから、法改正に向けて企業がすべきことはスキャナ保存・電子取引の要件を満たすクラウドサービスの導入です。特に電子取引は、2022年1月から2023年12月31日までの約2年間の猶予はあるものの、今後は全面的に紙での保存ができなくなるため早急に対策に取り組む必要があります。ここでは、法改正に向けた企業が行うべき事前準備をご紹介します。
スキャナ保存の要件を満たしたクラウドサービスの導入
スキャナ保存は、契約書や請求書などの「重要書類」と見積書や注文書などの「一般書類」が対象です。重要書類と一般書類では、保存要件が異なるのでそれぞれの要件に対応するクラウドサービスの導入が必要です。
また、スキャナ保存のやり方や機器の管理、責任者などを定めたスキャナ保存規定や事務処理マニュアルも整備しなくてはなりません。詳細については、国税庁のホームページにサンプルが用意されているのでご確認ください。
電子取引の要件を満たしたクラウドサービスの導入
電子データを保存するには、タイムスタンプ付与や訂正・削除などの履歴が残るシステムの利用といった改ざん防止対策がなされている必要があります。また、取引年月日・取引金額・取引先で検索できること、ディスプレイ・プリンターを備え付けることが必要要件です。
市販するクラウドサービスを利用する場合には、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の認証マークがついているものを選ぶのがおすすめです。法改正によって改ざん等の罰則が強化されたため、JIIMA認証を取得したクラウドサービスを利用することは、リスク回避に有効といえます。
請求業務の効率化は「請求管理ロボ」にお任せ!

2022年の電子帳簿保存法改正では、電子取引における電子データ保存が義務化されたため、クラウドツール・システムの導入がさらに加速すると予想されます。特にスキャナ保存・電子取引の要件は細かく定められているので、それぞれに対応するサービスの導入が必須です。
ROBOT PAYMENTが提供する「請求管理ロボ」であれば、電子帳簿保存法に対応した請求書作成が可能です。
「請求管理ロボ」は、毎月の請求業務を最大80%削減する請求管理システム(債権管理にも対応)です。請求書の発行や送付、集金、消込、催促などの売掛金管理を全て自動化し、人的作業を減らしてミスを防ぐとともに、経理業務の効率化を実現します。
加えて、SFA(販売管理システム)との連携により、自動で行われた請求業務の内容を会計システムに反映させることも可能です。これにより、煩雑なやり取りの削減と企業会計の透明化をサポートし、従業員がコア業務に専念できるようになります。
なお、コンビニ決済、クレジットカード決済、口座振替、銀行振込など、複数の決済手段に対応しているため、企業間取引のみならず、BtoC取引にも活用いただけます。
インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しており、これまでに700社以上の企業に導入され、年間取引請求金額は約2,770億円に上ります。経費の管理や帳簿付け、請求業務にお悩みの企業のご担当者様は、お気軽に「請求管理ロボ」にご相談ください。

※一部サービス提供元の運営記事です/PR