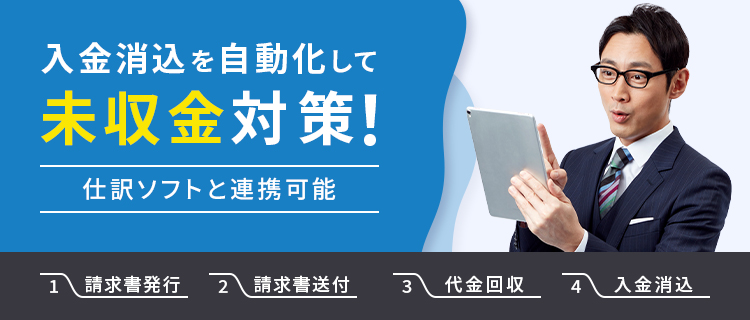売掛債権とは?売掛金や受取手形との違いを解説

ビジネスの現場で日々発生する取引。その多くは「掛取引」という形で行われ、企業の財務状態を大きく左右します。しかし「売掛債権」「売掛金」「受取手形」など、似たような用語が飛び交い、その違いを正確に理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。
本記事では、企業活動における重要な資産である「売掛債権」について、関連する用語との違いを交えながら、分かりやすく解説していきます。経理担当者はもちろん、ビジネスパーソン必見の基礎知識をお届けします。
売掛債権とは

売掛債権とは、企業が商品やサービスを掛売りした際に発生する、代金を回収する権利のことを指します。会計上は「資産」として計上されます。
例えば、A社がB社に100万円の商品を掛売りした場合、A社はB社に対して100万円分の売掛債権を持つことになります。この売掛債権は、期日が来てB社から実際に支払いを受けた時点で現金化されることになります。
売掛債権は企業の資金繰りに大きな影響を与える重要な項目です。債権の回収が滞ると、事業活動に必要な運転資金が不足する可能性があるため、適切な管理が求められます。特に「取引先の信用状況の確認」「回収期日の管理」「滞留債権の早期把握」「必要に応じた督促や法的手続きの検討」に注意が必要です。
また、決算書では「流動資産」の区分に計上され、通常1年以内に現金化されることが想定されています。企業の財務分析において、売上債権回転率や売上債権回転期間などの指標を算出する際の重要な要素となっています。
売掛債権と売掛金・受取手形の違い
売掛債権は企業が商品やサービスを掛売りした際に発生する、代金を回収する権利の総称を指す広い概念であるのに対し、売掛金や受取手形は売掛債権の中の一形態を指します。つまり、売掛債権は、売掛金と受取手形を合わせた包括的な概念となります。
例えば、ある企業の売掛債権が1,000万円あり、その内訳が「売掛金:800万円(請求書ベースの掛売り)」「受取手形:200万円(手形での支払い約束)」だったとしましょう。この場合、売掛金や受取手形は債権全体の一部を構成する要素となっています。
また、実務上の違いとしては以下の点が挙げられます。
1. 法的な保護
・売掛金:一般の民事債権としての保護
・受取手形:手形法による強い法的保護があり、不払いの際の手続きが明確
・売掛債権全般:手形や電子記録債権など、支払い手段によって異なる法的保護
2. 回収方法
・売掛金:通常の口座振込や現金での回収
・受取手形:期日前でも銀行で割引き現金化が可能
・売掛債権:手形の割引や電子記録債権の活用など、より幅広い資金化の手段がある
3. 管理方法
・売掛金:請求書や入金予定日での管理
・受取手形:手形期日や金額を専用の台帳で管理
・売掛債権:債権の種類ごとに異なる管理方法が必要
このように、売掛金と受取手形は売掛債権の一部を構成する要素であり、それぞれに特徴のある債権形態として使用されています。
売掛金と受取手形の違い
売掛金と受取手形は、どちらも企業が商品やサービスを販売した際に発生する債権であり、将来的に代金を受け取る権利を表しますが、「債権の形態」「法的拘束力」「支払い期日」「換金性」「信用度」の5点で重要な違いがあります。
まず、債権の形態については、口約束や契約書に基づくのが売掛金であるのに対し、受取手形は顧客が振り出した約束手形を企業が受け取ることで発生します。
次に、法的拘束力については、売掛金の法的拘束力は、受取手形に比べて弱いといえます。
売掛金の場合、顧客が支払いを延滞した場合、企業は督促や訴訟などの法的手段を取る必要がありますが、その手続きは煩雑で時間もかかります。一方、受取手形の場合は、支払いが滞ると銀行などを通じて強制的に回収することができます。
また、支払い期日については、その明確さに差があります。
売掛金の場合、支払い期日は明確に定められていない場合もあります。例えば、「翌月末払い」といった曖昧な取り決めの場合、具体的な期日は企業と顧客との間で解釈が異なる可能性があります。一方、受取手形の場合、支払い期日が手形に明確に記載されています。
さらに、換金性については、売掛金の換金性は受取手形に比べて低いといえます。
売掛金の現金化には、顧客からの支払いを受けるか、ファクタリングなどの金融サービスを利用する必要があります。一方、受取手形は、銀行などで割引することで、期日前に現金化することができます。
最後に、信用度については、受取手形のほうが売掛金より信用度が高いといえます。
売掛金の場合、顧客の信用度によって回収リスクが異なります。顧客の経営状況が悪化した場合、売掛金が回収できなくなる可能性があります。一方、受取手形は、手形を振り出した顧客の信用度だけでなく、手形自体にも信用力が加わるため、一般的に売掛金よりも信用度が高いとされます。
このように、売掛金と受取手形は、それぞれ特徴が異なるため、企業の取引内容や顧客の信用度などを考慮して、適切に使い分けることが重要です。
売掛債権を利用した資金調達方法

金融機関から融資を受ける場合には担保を設定する必要がありますが、売掛債権を担保にして資金を調達することができます。ファクタリングとABLと呼ばれる方法があり、以下にそれぞれについて解説します。
ファクタリング
ファクタリング(Factoring)とは、保証サービス提供会社が売上債権を保証して代金回収ができなくなるリスクを回避するもの、または未回収売掛金を買い取ってもらうサービスを指します。
ファクタリングを利用することで、取引先の倒産に備えて保証を取り付けてリスクヘッジを行い、あるいは売掛金を未回収のまま売却して現金化することができます。ファクタリングには売掛金を早期に現金化できる買取ファクタリングと、売掛債権を保証する保証ファクタリングの2種類があり、買取型は売掛債務をファクタリングサービス提供会社に売却して現金を受け取るものです。なお、買取型は更に2社間と3社間の2種類に分けられ、それぞれ手数料や契約内容が異なります。
保証型は保険のようなサービスで、取引先が信用面に不安があり、万が一倒産してしまって売掛金の回収ができなくなった場合に、売掛債権の焦げ付きを回避するために保証会社が保証金を支払うものです。
ABL
ABLとはAsset Based Lendingの略で、企業が所有する売掛債権や在庫、原材料、商品、設備機械といった動産などを担保にした融資の総称で、概ね動産・債権担保融資と同義です。ABLは米国で広く用いられている融資手法で、1970年~1980年頃から米国内に広まり、その後約40年で50兆円の規模になるまで成長しました。日本国内では政府・行政が中心となって主導しており、平成25年に日本銀行がABLの取り組みを促し、平成25年に金融庁がABLの積極的活用を発表して活用を推進し始めた、まだ歴史の浅い仕組みです。
ABLを活用することにより、不動産を保有していない企業でも、従来はあまり活用されていなかった動産などを担保にして融資を受けることができます。ABLは通常の融資と異なり、担保物件の価値の評価、企業と貸し手で企業の状況を逐次共有する担保資産の状況・業績の報告、担保物件の管理・保全に関するモニタリングが求められます。
売掛債権管理のコツ

滞りなく資金繰りをするためには、売掛債権を適切に管理する必要があります。以下にそのための売掛債権管理のコツを2つ解説します。
取引先の売掛債権を一覧にする
売掛債権のような流動資産を管理する1つ目の方法は、取引先の売掛債権を一覧表にまとめることです。これには売掛残金一覧表と売掛金年齢表(売掛金管理表)を作成する方法があります。
売掛残金一覧表は、取引先別に当月の売掛金発生額、前月の売掛金の未収金額、当月の回収金額、当月の未収金額を記入して一覧表にしたものです。これによって取引先ごとの売掛金の残高と、発生した売掛未収金額を把握することができます。売掛残金が把握できれば、支払いが滞留している取引先はないかということが分かります。
売掛金年齢表は、取引先ごとの未収入金額の残高を売上が発生した日、もしくは入金予定期日を基準として一定の期間で区切って管理する一覧表のことです。売掛金の発生後どの位の期間が経過しているかが分かるので、滞っている売掛金の状況を確認することができ、滞留している売掛債権の発見に繋がります。なお、売掛金年齢表は会計監査の際に提出することが求められることもあります。
取引先の売掛債権の限度額を設定する
与信取引で発生した売掛債権を適切に回収するために与信管理を行うことは、自社の資金繰りを滞らせないために必要なことです。与信管理を徹底するために重要なことは、取引先に対して売掛債権の限度額を設定して過度な与信リスクを負わないようにすることです。売掛債権の限度額は、取引で得られる収益機会とそれに伴う与信リスクを天秤にかけて判断し、自社の財務状況や取引先への依存度に基づいて設定します。
自社の財務能力を超えた取引を行うのは危険なので、取引のルールを決めて取引先の格付けをし、それに基づいて売掛債権の限度額の目安を決める方法が一般的です。
売掛債権の回収が遅れている場合の対処方法

売掛債権の回収が遅れている場合は、遅延損害金を請求できます。ここでは、その内容と実際の回収方法について解説します。
遅延損害金を請求できる
売掛債権の回収が遅れた場合、取引先に対して遅延損害金を請求できます。売掛債権は約束した期日までに入金されれば利息が付きませんが、遅れた場合は遅延損害金として利息が付き、売掛先(取引先)は遅延損害金として利息を支払う義務が生じます。
遅延損害金の利率は、前もって取り決めをしてなければ年6%の利率が設定されます。なお、遅延損害金が1年分を超えると元本に組み入れることができるようになります。つまり利息に利息が付くことになるのです。しかしながら、遅延損害金が付くような企業はもはや返済能力がないということも考えられ、そうなる前に前述したファクタリングなどの対策を立てておくほうが賢明でしょう。
遅れている売掛債権の回収方法
売掛債権を回収するには通常の商取引の手順に従って請求することが一般的ですが、売掛債権の回収が遅れている場合には正規の手順とは異なった方法で回収することが必要になってきます。その場合の回収の流れは以下のようになります。
まず、取引先からの未収金が見つかった場合、すぐに取引先に連絡を取ります。支払いが止まっていたのが単なる経理上のうっかりミスであればいいですが、取引先が倒産の準備に入ってしまっていたら売掛債権は回収できません。取引先に対して常に与信管理を継続的に行って信用度の低い取引先とは取引をやめる、あるいは売掛債権の限度額を減らすといった対応をすれば何か起こっても被害を抑えることができます。
取引先と連絡が取れて取引上の手続きに問題がなく、また取引先がキャッシュを持っているのに支払いを拒む場合は、請求書を内容証明郵便で送って請求の事実が書面で残るようにします。それでも取引先が支払いの意思を示さない場合は、法的手段を取ります。
具体的な措置としては、債権者の地位を移転する債権譲渡、債権者の保有財産の保有権や債権を代わりに行使する債権者代位権の行使、対当額の範囲での相殺、担保の提供を促す債権の補強などを行います。
売掛債権管理の効率化は「請求管理ロボ」にお任せ!

取引先が増えれば増えるほど売掛債権管理の重要度は増していきます。管理を怠っていては売掛債権の回収が滞り、売上は上げているのに資金繰りが詰まって黒字倒産という事態にもなりかねません。そこで、売掛債権の確実かつ効率的な管理方法をお探しなら、ぜひ「請求管理ロボ」の導入をご検討ください。
「請求管理ロボ」は、毎月の請求業務を最大80%削減する請求管理システム(債権管理にも対応)です。請求書の発行や送付、集金、消込、催促などの売掛金管理を全て自動化し、人的作業を減らしてミスを防ぐとともに、経理業務の効率化を実現します。
加えて、SFA(販売管理システム)との連携により、自動で行われた請求業務の内容を会計システムに反映させることも可能です。これにより、煩雑なやり取りの削減と企業会計の透明化をサポートし、従業員がコア業務に専念できるようになります。
なお、コンビニ決済、クレジットカード決済、口座振替、銀行振込など、複数の決済手段に対応しているため、企業間取引のみならず、BtoC取引にも活用いただけます。
インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しており、これまでに700社以上の企業に導入され、年間取引請求金額は約2,770億円に上ります。経費の管理や帳簿付け、請求業務にお悩みの企業のご担当者様は、お気軽に「請求管理ロボ」にご相談ください。

※一部サービス提供元の運営記事です/PR