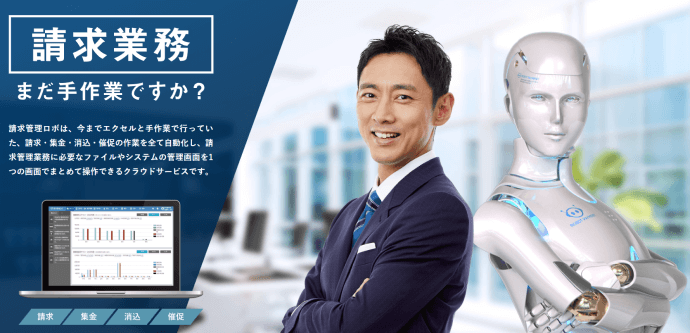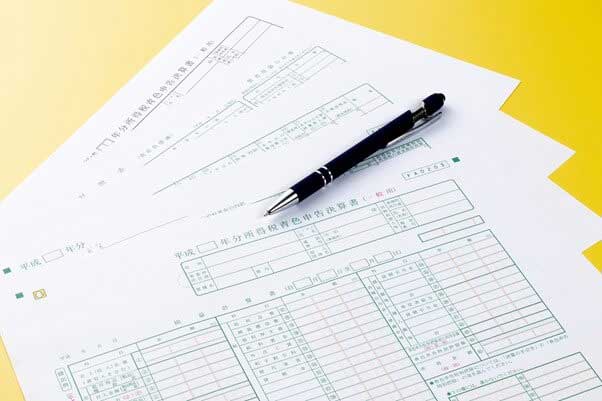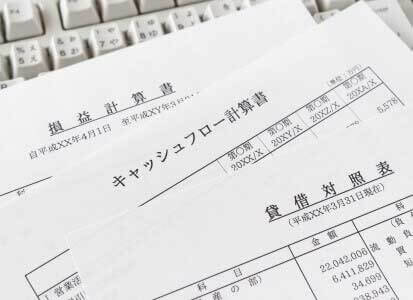経理職がおさえておきたい税務調査対応のポイント

税務調査とは、税務署による税務監査のようなものです。税務官は、税務調査によって、会社の税務申告が適正かどうかの調査を行います。税務調査には期日など一定の決まりがないため、いつ税務調査が入るかが分かりません。
また、普通は税務署から税務調査の告知があってから調査が行われますが、場合によっては事前通告なしに税務調査を行うこともあります。経理職にとっては、税務調査は緊張の瞬間ではないでしょうか。今回は、税務調査のための対策と税務調査時のポイントについて紹介します。
税務調査はいつ入るか分からない

税務調査は、事前告知がある場合がほとんどですが、場合によっては突然調査が行われることもあります。
経理担当をしている場合は、日々税務調査に向けてある程度の状況を把握しておくことが大切です。
少なくとも、過去5年間の申告の状況、取引先について、過去の税務調査の実態については把握しておくと良いでしょう。
事前対策1「売上げ計上の漏れ」
まず、税務調査では、いくつかの調査のポイントがあります。
中でも税務調査で調査対象になりやすいのが、売り上げに関するものです。
売上の計上時期がずれていたことにより、結果として売上計上漏れになる場合があります。売上の計上基準を確認して正しい時期に計上されているか確認しましょう。
また、過去に税務調査があった場合はどのように対応したのかも確認しておくと安心です。
事前対策2「交際費」
次に、指摘されやすいのが交際費。交際費という科目上、どういったお店で使われたものかどのような目的で使われたものか非常にグレーなゾーンで計上されているものもあるでしょう。
税務調査では、個人の経費が含まれていないかなど、不明確な領収書などが指摘の対象となります。
普段から、どこの会社の誰への接待か、何人で食事をしたのかなど、領収書などに明確に記載しておくと良いでしょう。
事前対策3「在庫の計上」
在庫の計上もまた、調査されやすいポイントです。
理由は、在庫の計上は操作がしやすく、操作したために売り上げを低く見せ、脱税の手段として使われることもあるからです。
調査では、在庫が正しいか仕入れや売り上げと合わせて細かく調査されることもあります。在庫の漏れについては税務調査前に事前に細かくチェックしておきたいところです。
事前対策4「架空の人件費」
多くの従業員や従業員の出入りが激しい会社では、チェックされやすいポイントのひとつです。
実際に、給料の水増しによって利益を低く計上している会社もあるからです。
疑いをかけられる前に、人件費の証明となる履歴書やタイムカード、給与台帳などはしっかりと準備しておきましょう。
経理業務の効率化は「請求管理ロボ」にお任せ!

請求書の発行や送付、集金、消込、催促などの売掛金管理を全て自動化し、人的作業を減らしてミスを防ぐとともに、経理業務の効率化を実現します。
加えて、SFA(販売管理システム)との連携により、自動で行われた請求業務の内容を会計システムに反映させることも可能です。これにより、煩雑なやり取りの削減と企業会計の透明化をサポートし、従業員がコア業務に専念できるようになります。
なお、コンビニ決済、クレジットカード決済、口座振替、銀行振込など、複数の決済手段に対応しているため、企業間取引のみならず、BtoC取引にも活用いただけます。
インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しており、これまでに700社以上の企業に導入され、年間取引請求金額は約2,770億円に上ります。経費の管理や帳簿付け、請求業務にお悩みの企業のご担当者様は、お気軽に「請求管理ロボ」にご相談ください。

※一部サービス提供元の運営記事です/PR