【2025年】サブスク管理システムおすすめ5選を比較
2025年2月17日
厳選した5つのサブスク管理システムについて、特徴や料金、対応した支払い方法を比較します。サブスク管理システムとは、サブスクリプションビジネスの契約・請求管理を効率化するツールです。比較ポイントやメリット、導入の注意点も解説します。
目次
サブスク管理システムの6つの比較ポイント
サブスクリプションビジネスを成功させるためには、適切な管理システム選びが重要です。ここでは、サブスク管理システムを比較する際に注目すべき6つのポイントを紹介します。
ポイント1.機能
サブスク管理システムを選ぶうえで、機能は最も重要なポイントのひとつです。必要な機能が備わっていないと、業務効率化の効果は得られません。機能が多ければ良いというわけではなく、機能が多すぎて操作や画面が煩雑だと、業務効率はむしろ落ちるかもしれません。
システムを比較する際は、自社のビジネスモデルに合った機能があるか確認しましょう。
具体的には、顧客管理、契約管理、請求管理、決済管理などの基本的な機能は必須です。加えて、分析機能やマーケティング機能など、事業の成長をサポートする機能があるとより良いでしょう。
ポイント2.金額や料金形態
サブスク管理システムの料金形態は、サービスによって大きく異なります。初期費用と月額利用料のバランスを考え、長期的な視点でコストを比較検討しましょう。
初期費用は無料のものから数十万円かかるものまでさまざまです。月額利用料は、ユーザー数や機能によって変動することが多いので、自社に合うプランを選びましょう。
無料トライアル期間を利用して、実際の使い勝手や費用対効果を確かめるのがおすすめです。
ポイント3.画面の見やすさ・使いやすさ
サブスク管理システムは、日々の業務で頻繁に使うツールです。そのため、画面の見やすさや使いやすさは、業務効率に直結します。
ダッシュボードで重要な指標を一目で確認できるか、操作は直感的でわかりやすいかなどをチェックしましょう。顧客情報や契約情報など、必要な情報にすぐにアクセスできるかどうかも重要です。
デモ画面やトライアルを利用して、操作してみると良いでしょう。このとき、実際に使う従業員の意見を取り入れるのも大切です。
ポイント4.対応した支払い方法
サブスクリプションビジネスでは、多様な支払い方法に対応することで、顧客満足度を高められます。対応している支払い方法が少ないと、顧客獲得の機会損失を招くおそれがあります。
クレジットカード決済、口座振替、コンビニ払いなど、主要な決済方法に対応していることを確認しましょう。海外展開を考えている場合は、現地の決済方法に対応しているかどうかも重要です。
たとえばサブスクペイは、クレジットカード決済や口座振替、コンビニ決済などの主要な支払い方法に対応しています。加えて掛け払い決済やSalesforce決済にも対応しているため、BtoBのビジネスにもおすすめです。
ポイント5.セキュリティ対策
サブスク管理システムは、顧客の個人情報や決済情報など、機密性の高い情報を扱います。そのため、強固なセキュリティ対策が施されているシステムを選ぶことが不可欠です。
情報漏えい対策、不正アクセス対策、データの暗号化など、具体的なセキュリティ対策の内容を確認しましょう。セキュリティに関する認証や規格を取得しているかどうかも、信頼性を判断するひとつの目安となります。
ポイント6.サポート体制
サブスク管理システムの導入後も、不明点やトラブルが発生する可能性があります。そのため、導入時だけでなく運用時のサポート体制も比較ポイントのひとつです。
問い合わせ方法(電話、メール、チャットなど)や対応時間、サポート内容(Q&A、マニュアル、訪問対応など)を確認しましょう。導入支援や運用コンサルティングなど、より手厚いサポートを提供しているサービスもあります。
サブスク管理システムを利用する5つのメリット
サブスク管理システムを導入することで、業務効率化や収益向上など、さまざまなメリットが得られます。ここでは、サブスク管理システムを利用する主なメリットを5つ紹介します。これらのメリットを理解することで、システム導入の重要性を再認識できるでしょう。
メリット1.業務効率化
サブスク管理システムは、煩雑な契約管理や請求業務を自動化し、業務効率を大幅に向上させます。手作業によるミスを減らし、コア業務に集中できる環境を構築できるためです。
たとえば、顧客情報の一元管理、契約更新の自動化、請求書の発行などがシステム上で完結します。これにより、事務作業にかかる時間や人件費を削減し、生産性の高い業務にリソースを集中できるようになります。
メリット2.さまざまな支払方法への対応
多様な料金プランや支払い方法に対応できることも、サブスク管理システムの大きなメリットです。顧客のニーズに合わせた柔軟な料金体系を提供することで、顧客満足度を高められます。
システムによっては、従量課金や月額制、年間払いなど、さまざまな料金プランに対応可能です。また、口座振替やクレジットカード払いなど、顧客が希望する支払い方法を選択できるため、顧客獲得の機会を逃しません。
メリット3.LTVの向上
サブスク管理システムは、LTV(顧客生涯価値。顧客が契約から解約までの間に自社にもたらす利益の総量)の向上に貢献します。
自動更新機能で更新手続きの手間を省き、顧客の継続利用を促進します。また、顧客データに基づいた最適な料金プランを提案することで、アップセルやクロスセルを促進し、客単価の向上が期待できます。
メリット4.収益の安定化
サブスク管理システムは、自動引き落としや支払いリマインダー機能により、未回収リスクを低減します。これにより、キャッシュフローが改善され、収益の安定化につながります。
毎月の支払いを自動化することで、顧客の支払い忘れを防ぎます。また、支払い期日が近づくと自動でリマインドメールを送信する機能もあり、確実な請求管理を実現できるでしょう。
メリット5.経営判断に役立つ
サブスク管理システムは、顧客データや売上データをリアルタイムで可視化します。蓄積されたデータは分析に活用でき、データに基づく経営判断をサポートします。
たとえば、顧客の利用状況や解約率、売上推移などを詳細に分析可能です。これらのデータをもとに、サービス改善や新規事業の立ち上げなど、より戦略的な意思決定が行えるようになります。
データからは「解約しそうな顧客」も見えてきます。データに基づきリテンションやアフターフォローをすることで、現場レベルでもサービス品質や解約率を改善できるでしょう。
サブスク管理システムの3つの注意点
サブスク管理システムは多くのメリットをもたらしますが、導入にあたっては注意すべき点もいくつかあります。ここでは、サブスク管理システムを導入する際の注意点を3つ紹介します。
注意点1.長期的にコストがかかる
サブスク管理システムは初期費用だけでなく、月額利用料やオプション料金など、継続的なコストが発生します。導入前に、長期的な視点で費用対効果を検討しましょう。
利用期間が長くなるほど総コストも増えます。無料プランや安価なプランから始めて、必要に応じて有料プランにアップグレードすることも検討しましょう。複数のシステムを比較検討し、自社の予算に合ったものを選ぶ必要があります。
注意点2.導入は業務プロセスの変更を伴う
サブスク管理システムの導入に伴い、既存の業務フローを変えなければなりません。新しいシステムに合わせて業務プロセスを見直す必要があるため、一時的に業務効率が低下する可能性も考えておきましょう。
システム導入前に、従業員への十分な説明や研修をしましょう。業務フローの変更点を明確にし、スムーズな移行を、組織としてサポートする必要があります。システムの導入によってかえって業務が煩雑になる、といった事態を避けなければなりません。
注意点3.情報漏えいのリスクを考える
サブスク管理システムは、顧客の個人情報や決済情報など、機密性の高い情報を扱います。そのため、情報漏えいのリスクを常に意識し、セキュリティ対策を徹底しなければなりません。
システム提供元のセキュリティ対策を確認するだけでなく、自社内での情報管理体制も強化しましょう。アクセス権限の設定やパスワード管理など、基本的なセキュリティ対策を徹底することが重要です。情報漏えいが発生した場合、顧客からの信頼を失い、事業継続が困難になるかもしれません。
サブスク管理システム比較5選
おすすめのサブスク管理システムを5つ、厳選して紹介します。サービスの特徴はもちろん、初期費用・月額料金・手数料といった費用、対応した支払い方法も紹介するので、比較検討の参考にしてください。
サブスクペイ

●業界最安水準の手数料
●選べる3つのプラン
●集客サイトをノーコードで作れる
サブスクペイは業界最安水準の手数料で利用できるサブスク管理システムです。支払い受付時の決済手数料は2.65%~。対応した支払い方法も幅広く、さまざまなビジネスモデルに対応できます。
支払い方法はクレジットカード決済や口座振替・振込、コンビニ決済といった一般的なものに加え、掛け払い決済やSalesforce決済にも対応。掛け払い決済は債権保証付きです。BtoCはもちろん、BtoBビジネスにもおすすめできます。
料金プランは3つあり、「既に顧客管理システムがある」「会員サイトや顧客管理システムの構築が必要」「申し込みサイトがあり、インボイス対応の領収書発行が必要」といった条件に応じて選べます。
特におすすめなのが「Professional」プランで、ノーコードでサブスクサイトを開設できます。ほかにも顧客属性や行動情報からネクストアクションを策定したり、LINEアカウントで顧客とコミュニケーションを取ったり、売上アップにつながる機能が豊富です。
このように、サブスクペイは単なる業務効率化だけでなく、売上アップ、経営判断の精度向上に大きく貢献します。
| 初期費用 | 月額料金 | 決済手数料 | 決済手段 |
|---|---|---|---|
| 要問い合わせ | 要問い合わせ | 2.65%〜 | クレジットカード決済、口座振替(バーチャル口座対応)、銀行振込、コンビニ決済、掛け払い決済、BtoB向けSalesforce決済 |
※バーチャル口座とは、顧客一人ひとりに専用の振込先口座番号を用意できるシステムです。どの顧客がいつ、いくら支払ったのかがわかりやすく、入金消込の効率化とミス防止につながります。
Scalebase
●販売・請求業務を一元管理しオペレーションを効率化
●変更予約や自動更新で処理漏れや誤請求を防止
●継続的な販売方法・料金体系の見直しが可能
Scalebaseは、BtoBサブスクリプションビジネスのための販売・請求管理システムです。分析レポート機能が搭載されており、主要な事業指標の可視化や請求書ベースの数字をもとに施策立案にも活用できます。
顧客ごとの契約内容・販売状況を時系列で可視化し把握できるため対応漏れを防げます。
ユーザー数による料金の変動はなく、部署ごとの導入も可能です。
| 初期費用 | 月額料金 | 決済手数料 | 決済手段 |
|---|---|---|---|
| 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | クレジットカード決済、口座振替 |
楽楽販売
●独自のルールをもとに請求処理や売上計上処理を自動化できる
●帳票発行はボタン一つ
●Excelからデータベース作成できプログラミング開発不要
楽楽販売は、金額計算や請求・売上計上を自動化するクラウド型の販売管理システムです。データステータス自動変更やアラートメールなどの機能が搭載されており、人為的ミスの削減と業務効率化が図れます。
売上や原価の計算も自動化でき複雑な計算式も設定可能なため計算ミスの削減・効率化できます。
月額費用は利用ユーザー数やデータベース作成数に応じて変動するため、費用のムダを抑えたい企業におすすめです。
| 初期費用 | 月額料金 | 決済手数料 | 決済手段 |
|---|---|---|---|
| 150,000円(税抜) | 70,000円〜(税抜) | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
サブスクONE
●顧客・契約データの一元管理でサブスクビジネス業務を自動化
●多様な課金プランに対応
●KPIツリー型のダッシュボードで課題の特定・改善を図る
サブスクONEは、サブスク事業の運営に必要な機能を提供するクラウド型プラットフォームです。多様な料金プラン・割引パターンに対応し、顧客利用データを基に従量・日割金額など自動で算出できます。
料金プランは2つあり、基本機能が揃ったライトプランと柔軟な課金プラン・システム連携に対応したフル機能を搭載したエンタープライズプランから選べます。サブスクビジネスを始めたい企業にもおすすめです。
| 初期費用 | 月額料金 | 決済手数料 | 決済手段 |
|---|---|---|---|
| 要問い合わせ | 98,000円〜(ライトプラン)/要問い合わせ(エンタープライズプラン) | 要問い合わせ | コンビニエンスストア振込、銀行口座振込、郵便局口座振込、銀行口座自動振替、クレカ決済、営業窓口での直接収納など |
Piano
●定期購読・買い切り型にも対応
●既存システムとのID統合もできる
●シングルサインオンに対応
Pianoは、メディアサイトに有効な施策ができるサービスです。価格設定の定義、試用期間の設定などを簡単にサイトへ反映できます。
サブスクライバーデータは顧客を継続的にトラッキングすることで、新規・既存・退会者それぞれにあったメールの配信が可能です。また、配信後メールの既読やアクションをチェックすることもできます。
| 初期費用 | 月額料金 | 決済手数料 | 決済手段 |
|---|---|---|---|
| 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | クレジットカード、PayPal、Apple Pay |
サブスク管理システムは業務効率化と経営判断の2面から比較しよう
サブスク管理システムを比較する際は、機能、料金、使いやすさ、支払い方法、セキュリティ、サポート体制の6つのポイントを確認することが重要です。これらのポイントを総合的に評価し、自社のビジネスに最適なシステムを選びましょう。
サブスク管理システムの導入は、業務効率化と経営判断の精度向上に大きく貢献します。システムを比較検討する際には、この2つの側面から、どれだけ自社のビジネスに貢献できるかを意識すると良いでしょう。
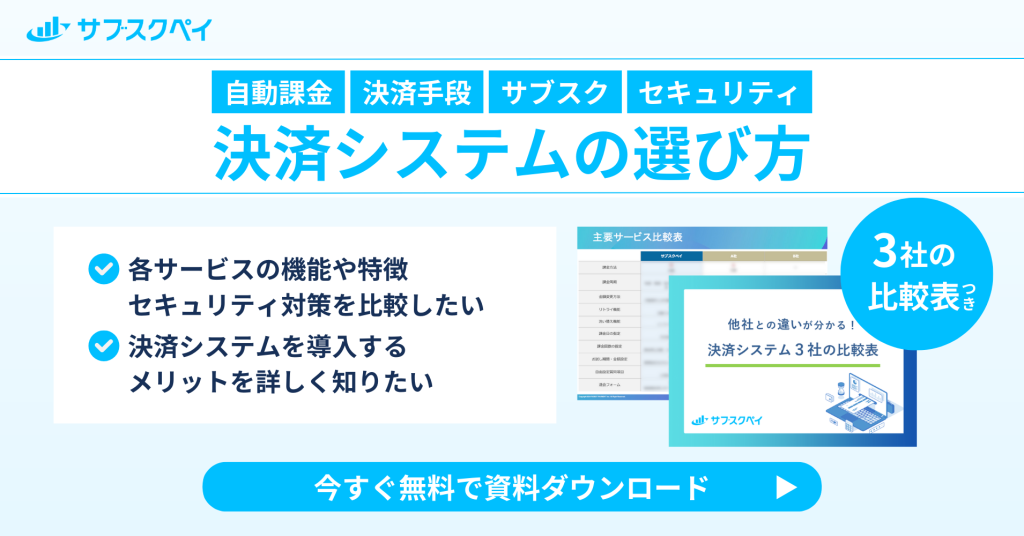
※一部サービス提供元の運営記事です/PR
【OREND(オレンド)について】
「OREND」は飲食店や小売、EC業界に関するトレンドや各サービスの比較情報などを発信する専門メディアです。キャッシュレス決済端末や予約管理システム、ネットショップ作成ソフトなど、これからの店舗・オンライン型ビジネスのDX化に必要なツールの仕組みや機能などを紹介しています。
「OREND」URL:https://orend.jp/
人気のコラム

2025年2月5日
コラム経理の目標設定はどう決める?目標の設定方...
経理職に就いている方のなかには、「目標を設定するのが難しい」と感じる方も多いのではないでしょうか。...

2025年2月2日
コラム繁忙期はいつ?業界別の特徴や忙しくなる理...
世の中にはさまざまな種類の仕事があり、そこで繁忙期という言葉を使う場面は多々みられます。 例...

2025年2月6日
コラム【2025年】入金消込自動化システムおす...
請求書と入金の照合作業「入金消込」。この作業は多くの企業で手作業で行われていますが、件数が多くなる...
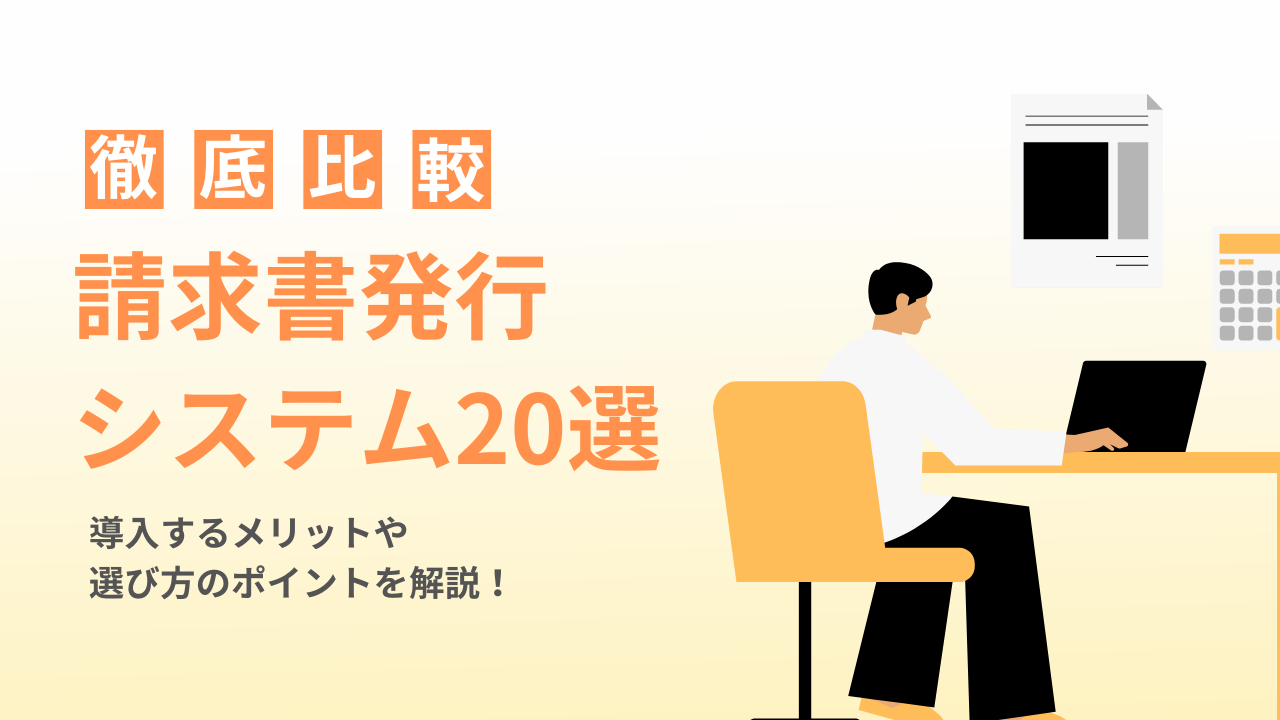
2025年2月5日
コラム【2025年】クラウド請求書発行システム...
近年、請求書発行業務の効率化やコスト削減、テレワークへの対応などのニーズから、クラウド請求書発行シ...
